割引せずに売れる店になる「適正客単価」設定の黄金法則
黄金法則の核心原理
適正客単価とは、
「利益が取れる価格設定」と
「手頃感の維持」の絶妙なバランスを指します。
これは単なる価格決定ではなく、
10年20年の長期経営を見据えた戦略的価格設定なのです。
1. 適正客単価の3つの条件
① 存続に必要な利益確保
- 粗利率70-80%の確保が基本指標
- 店舗運営費、人件費、設備投資を考慮した利益設定
- 「薄利多売の罠」から脱却:
大手のように仕入先を叩けない個人店は、付加価値で勝負
② 手頃感の維持(焼畑農業の回避)
- 客単価を上げすぎて顧客を失わない絶妙なライン
- 継続来店してもらえる価格帯の設定
- 一時的な売上より長期的な関係性を重視
③ 1人当たりの累計利益最大化
- 1回あたりの利益額 × 継続来店回数 = 顧客生涯価値
- 年間での総利益貢献度を最大化する視点
2. 価格設定の戦略的アプローチ
集客商品と収益商品の使い分け
価格は絶対的なものではないという重要原則:
- 集客商品:原価率高めでも話題性・集客力重視
- 収益商品:利益率高めで実際の収益源
- 話題商品:注文されなくても良い、マスコミ注目商品(1万円のプリン等)
実例:プリンの価格心理
- 500円のプリン単体では「高い」
- 隣に1,000円のプリンがあると500円が「安く」感じる
- さらに1万円のプリンがあると500円が「お手頃」に感じる
3. 粗利益向上の4つの実践方法
① 見せ方の改善
- 形、見た目、盛り付け方の変更で価値向上
- 五感を刺激する演出(鉄板の「ジュージュー」音など)
- わざと見せる演出(蕎麦打ちを客席から見えるように)
② ネーミングの変更
- 「お絵かきボード」→「筆談ボード」で用途提案
- 商品名・サービス名の最適化で価値認識向上
③ 伝え方の改良
- 商品自体の説明ではなく「得られるご利益」を伝える
- 「だから何がいいのか」を明確に表現
④ セット化・絞り込み
ライザップ方式の応用:
- 食事管理(単品3万円)+ パーソナルトレーニング(単品3万円)
- ↓ セット化・コンセプト化
- 「60日で理想の体」(60万円)
4. メニュー配置の戦略
目線誘導による客単価向上
- 人の目線は上から下、左から右
- 安い商品を最上段に配置するのは逆効果
- 頼んでもらいたい商品を一番目立つ位置に
改善例:マグロ丼専門店
- 【改善前】最上段:ワンコインマグロ丼500円(目立つ位置)
- 【改善後】最上段:天然マグロ丼1,800円(本当に食べて欲しいもの)
おすすめ商品の示し方
- 全て一律に掲載しない
- 注文してほしい商品を目立たせる
- おすすめする理由を伝える
- セット商品を作る
5. 価格競争から脱却する仕組み
割引に頼らない集客の実現
- 商品自体の価値向上で適正価格を維持
- リピート客との関係性構築で価格以外の価値提供
- 独自性・専門性で競合との差別化
適正間隔での来店促進
美容室の例:
- 適正周期(2ヶ月)でのご案内をしない場合
- 年6回来店 → 年4回来店に減少
- 1人当たり年間6万円 → 4万5千円(1万5千円の損失)
6. 長期継続のための価格戦略
10年20年を見据えた価格設定
- 一時的な値下げ競争に巻き込まれない
- ブランド価値の維持・向上
- 顧客との信頼関係構築を最優先
商品構成の最適化
- ものだけでなく、ノウハウ・サービスを付加
- 形のないものと組み合わせて粗利率向上
- コンセプト化による高付加価値化
まとめ:適正客単価設定の成功公式
適正客単価 =
【必要利益を確保できる価格】×【継続来店してもらえるバランス】×【顧客が感じる価値】
この公式を実現するには:
- 財務面:粗利率70-80%確保
- 心理面:価格の相対性を活用した戦略的メニュー構成
- 関係面:価格以外の価値(サービス、関係性、体験)の充実
- 時間面:長期的視点での顧客生涯価値最大化
割引に頼らず、
お客様にも喜ばれる適正価格で
持続可能な経営を実現することこそが、
真の「適正客単価設定の黄金法則」なのです。
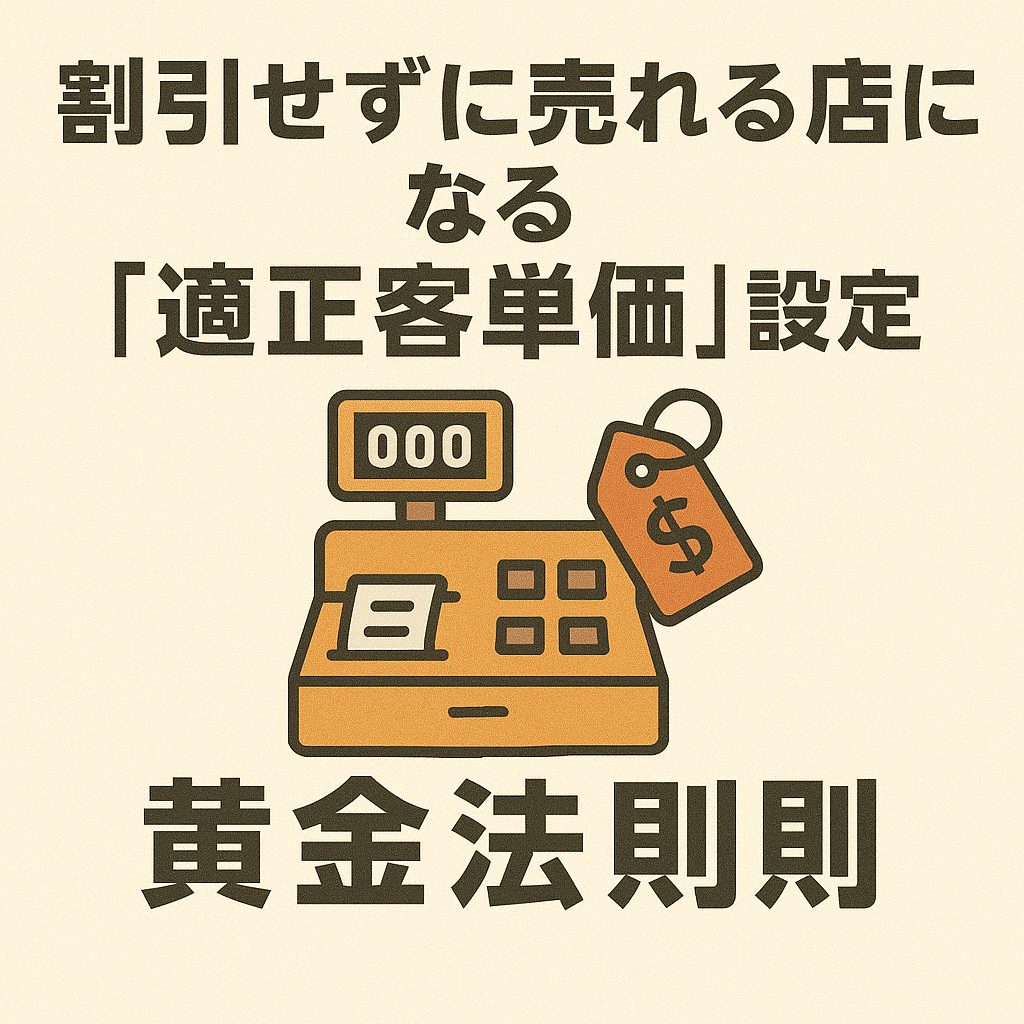
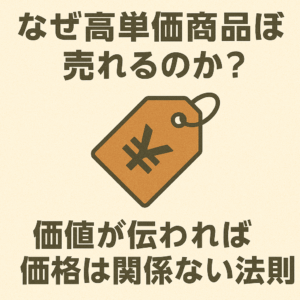
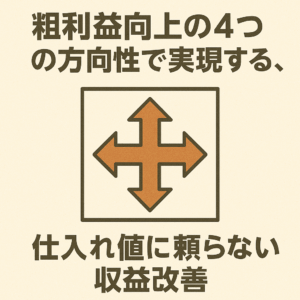
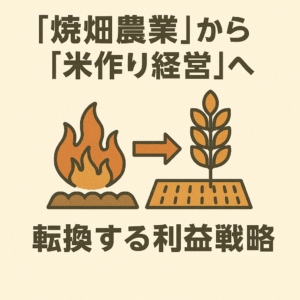
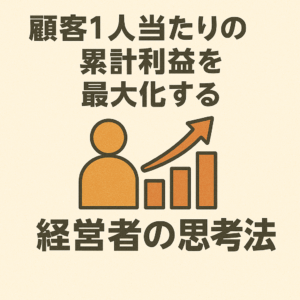
コメント