~「迷わない」スタッフを育てる明確なルール作り~
「スタッフがいちいち聞いてくるんです。自分で判断してくれればいいのに…」
でも実は、スタッフが自分で判断できないのは、あなたが「判断基準」を教えていないからかもしれません。今日は、スタッフが迷わず行動できる「判断基準の作り方」をお教えします。
なぜスタッフは「いちいち聞いてくる」のか?
スタッフの本音を理解する
多くの経営者は「なんでこんな簡単なことを聞いてくるの?」と思いがちです。でも、スタッフ側の気持ちを考えてみてください:
スタッフの不安:
- 「間違った判断をして怒られたらどうしよう」
- 「お客様に迷惑をかけてしまったらどうしよう」
- 「どこまでが自分の判断範囲なのかわからない」
- 「前に同じような時、店長は違う対応をしていた」
つまり、スタッフは「判断したくない」のではなく、 「判断基準がわからない」 のです。
「察してちゃん」経営の落とし穴
多くの経営者が無意識にやってしまうのが、この「察してちゃん」経営:
❌ 「普通に考えればわかるでしょ」 ❌ 「前にも説明したよね」 ❌ 「常識で判断して」
でも、あなたの「普通」「常識」は、スタッフには伝わっていません。10年の経験がある店長と、入社3ヶ月のスタッフでは、判断基準が全く違うのです。
効果的な判断基準作りの5つのステップ
ステップ1:「よく聞かれること」をリストアップ
まずは、スタッフからよく質問される内容を1週間記録してみましょう。
よくある質問例:
- 「在庫がない時はどうしますか?」
- 「お客様が怒っている時の対応は?」
- 「予約が重複した時は?」
- 「割引の適用基準は?」
- 「返品・交換の対応は?」
ステップ2:3段階の権限レベルを設定
すべての判断を同じレベルで扱うのではなく、リスクや重要度に応じて段階分けします。
【レベル1】スタッフ判断OK
- お客様への基本的な案内
- 通常の商品説明
- 簡単な要望への対応
【レベル2】リーダー・副店長判断
- 商品の交換・返品
- 特別な要望への対応
- 軽微なクレーム対応
【レベル3】店長判断必須
- 返金対応
- 重大なクレーム
- 価格変更や特別割引
ステップ3:具体的な判断基準を文章化
曖昧な表現ではなく、誰が読んでも同じ判断ができる基準を作ります。
悪い例: 「お客様が困っていたら、適切に対応する」
良い例:
【商品切れの場合の対応】
1. 類似商品を2つ以上提案する
2. 入荷予定日を確認して伝える
3. 予約受付が可能かを案内する
4. 代替案でも満足いただけない場合は店長に相談
ステップ4:判断の「理由」も説明する
ただルールを示すだけでなく、なぜその基準なのかも伝えることで、応用力が身につきます。
例:クレーム対応の基準
【なぜこの基準なのか】
・最初は謝罪から入る→お客様の気持ちを受け止めるため
・事実確認を丁寧に行う→誤解によるトラブルを防ぐため
・解決策は複数提示する→お客様に選択権を持っていただくため
ステップ5:実際の場面で練習する
ルールを作っただけでは身につきません。実際の場面を想定した練習が重要です。
ロールプレイング例:
- あなたがお客様役、スタッフが対応役
- 様々なパターンを演習
- 判断に迷った時の対処も練習
具体的な判断基準の作成例
【飲食店】お客様対応の判断基準
料理に関するクレーム対応
【レベル1:スタッフ対応OK】
・「少し時間がかかっている」程度の待ち時間
→「申し訳ございません、もう少々お待ちください」
→進行状況を厨房に確認して報告
【レベル2:リーダー相談】
・「注文と違う料理が来た」
→即座にお詫び→正しい料理を準備開始→リーダーに報告
【レベル3:店長判断】
・「髪の毛が入っている」など衛生面の問題
→お詫び→料理をお下げ→即座に店長に連絡
会計・料金に関する判断基準
【スタッフ判断OK】
・ポイントカードの適用
・通常メニューの説明と料金案内
・お会計の基本操作
【リーダー判断】
・団体割引の適用
・ちょっとしたサービス(ドリンク1杯など)
・常連客への特別対応
【店長判断必須】
・返金対応
・大幅な割引
・料金に関するトラブル全般
【美容室】技術・サービスの判断基準
お客様からの技術的要望
【スタッフ対応OK】
・基本的なスタイルの相談
・シャンプー・ブローの希望
・予約時間の調整(30分以内)
【先輩スタッフ相談】
・難易度の高いカラーリング
・大幅なスタイルチェンジ
・アレルギーに関する相談
【店長判断必須】
・技術的なクレーム
・髪や頭皮のトラブル
・料金に関わる特別対応
権限移譲を成功させる「段階的」アプローチ
第1段階:観察期間(1週間)
新しい判断基準を渡したら、最初の1週間は「観察」に徹します。
やること:
- スタッフの判断を見守る
- 間違いがあっても即座に訂正しない
- 後で一緒に振り返る
やってはいけないこと:
- 「それ、基準と違うでしょ」と即座に指摘
- スタッフの前でお客様に謝る
- 基準を無視して店長が対応する
第2段階:フィードバック期間(2週間)
毎日の振り返り(5分)
- 「今日はどんな判断をしましたか?」
- 「基準通りに対応できましたか?」
- 「迷ったことはありましたか?」
改善ポイントの共有
- 良かった判断を具体的に褒める
- 改善点は一緒に考える
- 基準の修正が必要な場合は更新
第3段階:自立運営期間(1ヶ月〜)
月1回の見直し
- 基準の有効性をチェック
- 新しい問題への対応を追加
- スタッフからの改善提案を聞く
よくある失敗パターンと対策
失敗パターン1:基準が曖昧すぎる
問題例: 「お客様の満足度を最優先に判断する」
改善例: 「お客様が不満を示された場合は、まず謝罪し、具体的な解決策を2つ以上提示する。解決策の実行には金額に応じて以下の権限で対応…」
失敗パターン2:例外処理ばかりする
問題: 基準を作ったのに、店長が「今回は特別」と例外対応を頻発
対策: 例外を作る場合は、その理由をスタッフに説明し、基準の見直しを検討
失敗パターン3:権限範囲が狭すぎる
問題: 何でもかんでも「店長判断」にしてしまう
対策: 小さなリスクは積極的にスタッフに任せる。失敗は学習の機会と考える
判断基準の「見える化」テクニック
1. ラミネート加工した基準表を作成
重要な判断基準は、A4用紙にまとめてラミネート加工し、レジ周りに設置します。
2. フローチャート形式で整理
複雑な判断は、フローチャートで視覚化すると理解しやすくなります。
お客様からクレーム
↓
まずは謝罪・傾聴
↓
内容を確認
↓
料理の問題? → YES → レベル2対応
↓ NO
会計の問題? → YES → レベル3対応
↓ NO
サービス改善で解決? → YES → レベル1対応
3. 「判断基準ノート」の活用
新しい事例が起きた時に、その都度ノートに記録し、基準をアップデートしていきます。
権限移譲成功の指標
1ヶ月後の変化
スタッフの変化: □ 迷いなく基本対応ができる □ 自分から「こう対応しました」と報告する □ お客様からの評価が向上する
あなたの変化: □ スタッフからの質問が明らかに減る □ 安心してお店を任せられる時間が増える □ より重要な業務に集中できる
6ヶ月後の目標
組織の変化: □ スタッフが新しいスタッフに基準を教える □ 基準の改善提案がスタッフから出る □ お客様満足度が向上する □ 売上・利益が安定または向上
実際の成功事例
カフェ「○○珈琲店」の事例
導入前の課題:
- 1日平均15回の「店長への質問」
- アルバイトが委縮して積極性がない
- 店長が休むとサービスレベルが低下
判断基準導入後(3ヶ月):
- 質問回数が1日3回に減少
- アルバイトから改善提案が出るように
- 店長不在日でも売上維持
店長のコメント: 「最初は基準作りが面倒でしたが、一度作ってしまえば楽になりました。スタッフも自信を持って対応できるようになり、お客様からの評価も上がっています」
今日から始められる3つのアクション
アクション1:質問記録を開始
今日から1週間、スタッフからの質問内容と回数を記録してください。
アクション2:最重要な基準を1つ決める
最も頻繁に聞かれる質問について、明日までに具体的な判断基準を作成してください。
アクション3:スタッフとの相談時間を設定
「みんながもっと自信を持って判断できるよう、基準を一緒に作りたい」と相談してください。
まとめ:明確な基準が生む安心と成長
判断基準の明確化は、スタッフとあなたの両方に安心をもたらします。
スタッフにとって:
- 迷わずに行動できる安心感
- 自分の判断に自信が持てる
- 成長実感を得られる
あなたにとって:
- 細かい判断から解放される
- より重要な仕事に集中できる
- 組織としての底上げを実現
今日から、スタッフが「迷わず判断できる」環境作りを始めませんか?明確な基準があれば、スタッフは必ず期待以上の成長を見せてくれます。








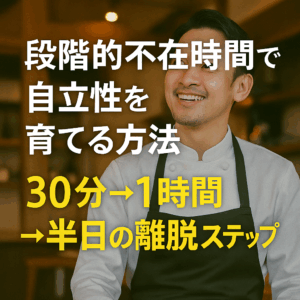

コメント