「あー、また急に○○の件で呼び出された…」
今日も朝から、予定していた仕事が全然進まない。スタッフからの「社長、ちょっと」「店長、これどうしたら…」という呼び出しの連続。
気がつけば夕方。「今日も結局、売上アップの企画が全然できなかった…」
そんな毎日を送っていませんか?
実は、これらの「突発的業務」の90%は本来起きる必要のないもの。そして残りの10%も事前に対処できるものなのです。
今日は、あなたを突発的業務から解放し、本来やるべき仕事に集中できる仕組み作りをお教えします。
「突発的業務」の正体を知る
そもそも「突発的」ではない
多くの経営者が「突発的」だと思っている業務の実態:
【よくある "突発的" 業務】
・「これってどうしたらいいですか?」の相談
・「お客様からクレームが...」の報告
・「機械が動かなくなりました」の連絡
・「材料が足りません」の連絡
・「予約の変更をしたいお客様が...」の対応
でも冷静に考えてみてください。これらは本当に「予測不可能」でしょうか?
慢性化している「突発」の特徴
慢性化の危険信号チェック □ 同じような内容で月3回以上呼ばれる □ 「いつものあれ」で通じてしまう問題がある □ スタッフが自分で判断せずすぐに相談してくる □ 同じ時間帯によく呼ばれる □ 決まった人からの相談が多い
1つでも当てはまれば、それは「突発的」ではなく「慢性的」問題です。
なぜ突発的業務が慢性化するのか?
原因①:社長が「何でも屋」になっている
悪循環のサイクル
問題発生 → 社長が即座に解決 → スタッフが学習機会を失う →
また同じ問題で社長に相談 → 社長がまた解決 → エンドレス
社長の「親切すぎる対応」が、実はスタッフの成長を妨げているのです。
原因②:判断基準が明確でない
スタッフは「どこまで自分で判断していいか分からない」から、とりあえず社長に聞いてしまいます。
よくある曖昧な指示
- 「臨機応変に対応して」
- 「常識的に考えて」
- 「お客様のことを第一に」
- 「適切に判断して」
これでは、スタッフは判断できません。
原因③:失敗を恐れる文化
「間違えたら怒られる」という空気があると、スタッフは自分で判断することを避けます。
突発的業務を根絶する「3段階システム」
第1段階:「突発業務ログ」で見える化
まずは1週間、あなたに舞い込む突発的業務を全て記録してください。
記録フォーマット
【突発業務ログ】
日時:
内容:
対応時間:
相談者:
本来の担当者:
再発の可能性:高・中・低
1週間後の分析
- 最も多い突発業務は?
- 特定の人からの相談が多くないか?
- 特定の時間帯に集中していないか?
- 事前に防げたものはどれか?
第2段階:「権限移譲マップ」の作成
スタッフがどこまで自分で判断していいかを明確にします。
権限レベル設定例
【レベル1:新人スタッフ】
・1,000円以下の返金:自分で判断OK
・簡単な商品説明:マニュアル見ながらOK
・基本的な清掃:指示通りに実行
【レベル2:経験者スタッフ】
・5,000円以下の返金:自分で判断OK
・お客様のカスタム要望:可能な範囲で対応
・新人への指導:基本業務について
【レベル3:ベテランスタッフ】
・10,000円以下の返金:自分で判断OK
・クレーム対応:初期対応は全て任せる
・シフト調整:社長に報告後実行
第3段階:「事前対処システム」の構築
起きる前に対処する仕組みを作ります。
予防システム例
【在庫管理の事前対処】
・発注点を設定(残り○個になったら自動発注)
・週2回の在庫チェック日を設定
・発注は毎週火曜・金曜に実施
・担当者が休む場合の代理人を事前指名
【機械メンテナンスの事前対処】
・月1回の定期点検日を設定
・異常サインの早期発見チェックリスト
・修理業者の連絡先をスタッフ全員が把握
・代替機器の準備
業種別「突発業務撲滅」成功事例
【居酒屋】の成功事例
Before:1日平均15回の突発対応
よくある突発業務:
・「お客様から〇〇の注文ですが、売り切れです」
・「生ビールの泡が出ません」
・「お客様がお怒りです」
・「レジの操作が分からない」
・「予約のお客様がいらっしゃいません」
After:突発対応を1日3回以下に激減
導入した仕組み
【売り切れ対策】
・15時に在庫チェック → 売り切れ予想品目をリストアップ
・お客様には入店時に「本日のおすすめ」で先に案内
・売り切れ商品には代替メニューを必ず提案
【機器トラブル対策】
・開店前の機器点検チェックリスト導入
・各機器の簡単な対処法をラミネート掲示
・修理業者直通番号を各持ち場に設置
【クレーム対策】
・初期対応マニュアル作成
・謝罪→傾聴→解決案提示の3ステップ
・5,000円以下の対応は現場スタッフに権限移譲
【美容室】の成功事例
Before:施術中に1日平均10回中断
よくある突発業務:
・「お客様が遅刻されています」
・「カラー剤が足りません」
・「次のお客様から電話です」
・「シャンプー台の調子が悪いです」
・「予約時間を変更したいお客様が...」
After:施術中断を1日2回以下に
導入した仕組み
【予約管理システム】
・遅刻15分で自動的に次予約と調整
・カラー剤は前日に必要量を準備
・電話は受付専任スタッフが対応
・機器の定期メンテナンス日を設定
【権限移譲システム】
・30分以内の予約変更は受付スタッフが対応
・軽微なクレームは担当スタイリストが完結
・次回予約の調整も現場で完結
「自立型スタッフ」を育てる指導法
ステップ1:まず「考えさせる」
スタッフから相談された時の対応を変えます。
❌ 従来の対応 「それは△△すればいいよ」(即答)
⭕ 改善した対応 「君はどう思う?」(逆質問) ↓ スタッフが考える ↓
「その考えで正解。次からは自分で判断していいよ」
ステップ2:「失敗OK」の環境作り
【失敗を恐れない文化の作り方】
・「完璧より行動」を合言葉に
・失敗した時は「どう改善する?」と建設的質問
・良い判断をした時は必ず褒める
・失敗事例を全員で共有し学習機会に変える
ステップ3:段階的に権限を拡大
【権限拡大プロセス】
第1段階:簡単な判断から任せる
第2段階:成功体験を積ませる
第3段階:少し難しい判断も任せる
第4段階:結果の責任も一緒に負わせる
第5段階:完全に権限移譲
突発業務ゼロの「理想システム」設計図
朝礼で1日の「想定問題」を共有
【朝礼での確認事項】
・今日起こりそうな問題は?
・対処法の確認
・担当者の明確化
・社長が不在の時間帯の責任者決定
「問題対処マニュアル」の整備
【問題別対処マニュアル例】
1. 機器故障 → まず○○を確認、ダメなら△△に連絡
2. お客様クレーム → 3ステップ対応法実行
3. スタッフ急病 → 代替要員リストから連絡
4. 停電 → 非常時対応チェックリスト実行
5. 在庫切れ → 代替品提案リストを活用
月1回の「突発業務撲滅会議」
【会議内容】
・今月発生した突発業務の振り返り
・改善できた事例の共有
・新たな予防策の検討
・スタッフの自立度評価
・来月の予防計画立案
今すぐできる実践チェックリスト
【今日からスタート】突発業務の記録開始
□ 突発業務ログ用紙を準備 □ スマホのタイマーで対応時間を測定 □ 1週間継続して記録 □ パターンを分析
【今週中に完成】権限移譲マップ
□ スタッフ別のスキルレベル把握 □ 業務別の判断権限レベル設定 □ 権限移譲マップの作成 □ スタッフへの説明・共有
【今月中に構築】事前対処システム
□ 頻発する突発業務TOP3を特定 □ 各業務の事前対処法を考案 □ 必要な道具・システムを準備 □ スタッフ教育・訓練の実施
まとめ:「突発」から「計画」への転換
突発的業務に振り回される経営者と、全てを計画的に処理する経営者。その違いは「仕組み化の有無」です。
突発業務に振り回される店の特徴
- 社長が忙しそうに見えるが成果が出ない
- スタッフが依存的で成長しない
- 同じ問題が何度も繰り返される
- 長期的な改善計画が立てられない
計画的に運営される店の特徴
- 社長が本来業務に集中できる
- スタッフが自立的で頼もしい
- 問題が起きても冷静に対処
- 継続的な成長と改善が実現
今日からできる3つのアクション
- 突発業務ログの記録開始(所要時間:記録は1件30秒)
- 最多頻発業務の対処法検討(所要時間:15分)
- スタッフへの権限移譲範囲の明確化(所要時間:30分)
1週間後、あなたの1日は「突発対応の連続」から「計画的な業務遂行」に変わっているはずです。
そして1か月後には、スタッフから「どうしたらいいですか?」ではなく「こうしました」という報告が増えていることでしょう。
あなたを突発業務から解放し、本来の経営者業務に専念できる環境を、今すぐ作り始めましょう!









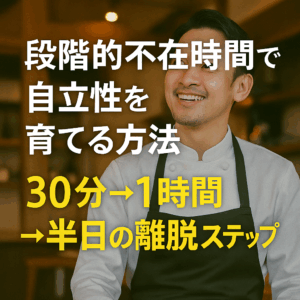
コメント