「また問題が起きた…」
そんな時、あなたはどんな気持ちになりますか?
「なんで今日に限って…」「忙しいのに余計な仕事が増えた」「うちのスタッフはなんでこんなミスばかり…」
そんなため息をついていませんか?
でも、ちょっと待ってください。実は、その「問題」こそが、あなたのお店を劇的に改善する最高のチャンスなんです。
今日は、問題を「厄介なもの」から「宝の山」に変える考え方をお教えします。
なぜ多くの経営者は問題を嫌がるのか?
問題=悪いこと という思い込み
私たちは子供の頃から「問題を起こしてはいけない」と教えられてきました。だから無意識に:
- 問題が起きると焦る
- 隠そうとする
- 表面的な対処で終わらせる
- 同じ問題が再発する
- さらに大きな問題に発展
この悪循環に陥っている経営者がほとんどです。
成功している経営者の「問題観」
一方、繁盛店の経営者はこう考えています:
「問題が起きた!ラッキー!改善点が見つかった!」
この考え方の違いが、成功と失敗を分けているのです。
問題が「宝の山」である3つの理由
理由①:隠れていた弱点が表面化する
問題が起きるということは、これまで見えなかった「お店の弱い部分」が明らかになったということ。
具体例:居酒屋での出来事
【問題】新人スタッフが注文を間違えて、お客様にお叱りを受けた
【従来の対処】
→ 新人に「気をつけて」と注意するだけ
【改善思考の対処】
→ なぜ間違えたのか?注文システムに問題はないか?
→ オーダー用紙が分かりにくいことが判明
→ 新しい分かりやすいオーダーシステムを導入
→ 全スタッフの注文ミスが激減!
問題をきっかけに、根本的な改善ができたのです。
理由②:スタッフの成長機会になる
問題対応は、スタッフにとって最高の「実践教育」です。
美容室での実例
【問題】予約の時間にお客様が来店されない
【スタッフの成長プロセス】
1. 慌てて上司に相談(依存段階)
2. 自分で電話確認してみる(自立段階)
3. 事前確認システムを提案(貢献段階)
4. 他のスタッフにもノウハウ共有(指導段階)
問題を通じて、スタッフが依存型から自立型、さらに貢献型へと成長していきます。
理由③:お客様との信頼関係が深まる
適切な問題対応は、お客様との関係をより強固にします。
信頼関係向上の法則
問題発生 → 真摯な対応 → 解決 → 信頼度UP → 常連客化
実際に、問題をきっかけに「この店は本当に誠実だ」と感じて、より愛着を持ってくださるお客様は多いのです。
問題を「改善チャンス」に変える5つのステップ
STEP1:感情と事実を分ける
問題が起きた瞬間は誰でも感情的になります。でも、まずは深呼吸。
感情的な反応
- 「なんでこんなことが…」(落胆)
- 「またあのスタッフが…」(怒り)
- 「お客様に申し訳ない…」(不安)
事実ベースの捉え方
- 何が起きたのか?(事実確認)
- いつ、どこで、誰が関わったのか?(状況整理)
- どんな影響があったのか?(影響度測定)
STEP2:「なぜ?」を5回繰り返す
表面的な原因で止まらず、根本原因まで掘り下げます。
実例:料理の提供が遅れた問題
1. なぜ料理が遅れた? → 厨房が混雑していたから
2. なぜ厨房が混雑した? → 同じ時間に注文が集中したから
3. なぜ注文が集中した? → ピークタイムの予測ができていなかったから
4. なぜ予測ができていなかった? → データを取っていなかったから
5. なぜデータを取っていなかった? → データの重要性を認識していなかったから
【根本原因】データに基づく運営ができていない
【改善策】売上データの分析システム導入
STEP3:関係者全員でアイデア出し
問題解決は一人で考えず、チーム全体で取り組みます。
効果的なアイデア出しの方法
【参加者】関係するスタッフ全員
【時間】15-30分(短時間集中)
【ルール】
・批判禁止(どんな意見もまずは受け入れる)
・量を重視(質は後で考える)
・他人のアイデアに便乗OK
・実現可能性は後で判断
STEP4:実現可能な解決策を選ぶ
出てきたアイデアを整理し、実際に実行できるものを選択します。
選択基準
- コスト:予算内で実現可能か?
- 時間:いつまでに実施できるか?
- 効果:問題解決にどの程度役立つか?
- 実行難易度:現在のスタッフで対応可能か?
STEP5:実行後の効果測定
解決策を実行したら、必ず効果を測定します。
測定項目例
- 同様の問題の発生回数
- お客様満足度の変化
- スタッフの業務効率の変化
- 売上や利益への影響
問題レベル別の対応方法
レベル1:軽微な問題(日常的なミス)
例:注文の聞き間違い、軽微な接客ミス
対応方針
- その場で解決
- スタッフの学習機会として活用
- 簡単な改善で再発防止
レベル2:中程度の問題(業務に影響)
例:機器の故障、スタッフの急な欠勤
対応方針
- 即座にチーム対応
- 代替手段の実行
- システム改善を検討
レベル3:重大な問題(経営に影響)
例:食中毒、大きなクレーム、火災
対応方針
- 経営陣が直接対応
- 外部専門家のサポート活用
- 抜本的な制度改革を実施
「問題歓迎文化」を作る方法
スタッフに伝えるべきメッセージ
❌ 従来のメッセージ 「問題を起こさないように気をつけろ」
⭕ 改善メッセージ 「問題が起きたら、必ず報告してほしい。隠さずに教えてくれるスタッフを評価する」
問題報告を促進する仕組み
①報告しやすい環境作り
- 責める文化をやめる
- 「なぜ?」の質問は責任追及ではなく改善のため
- 報告してくれたことをまず感謝する
②問題解決への参加促進
- 解決策のアイデア出しに参加してもらう
- 良いアイデアを出したスタッフを表彰
- 改善結果をスタッフ全員で共有
③学習機会としての活用
- 「今回の問題で何を学んだか」を振り返る
- 失敗を次への糧にする文化醸成
- 成功事例として社内に広める
実際の成功事例
【事例1】カフェの「コーヒーが薄い」クレーム
問題発生 お客様から「今日のコーヒーが薄くて美味しくない」とのクレーム
従来の対応なら… → 謝罪して作り直し、スタッフに「注意して作って」と指導
改善思考での対応
- 原因分析:なぜ薄くなったのか?
- 発見:豆の計量が人によってバラバラだった
- 解決策:専用スプーンと計量の標準化
- 結果:全スタッフが同じクオリティで提供可能に
- 波及効果:お客様から「いつも安定して美味しい」と評価アップ
【事例2】美容室の「予約ダブルブッキング」
問題発生 同じ時間に2人のお客様の予約が入ってしまった
改善思考での対応
- 原因分析:予約システムの運用ルールが曖昧
- 解決策:予約受付のチェックリスト作成
- システム改善:予約確認の二重チェック体制
- 結果:ダブルブッキング完全防止
- 波及効果:お客様の信頼度向上、予約数増加
今すぐできる「問題歓迎」実践法
【実践①】問題収集ノートの作成
用意するもの:普通のノート1冊
記録内容
- 日時
- 問題の内容
- 関係者
- 原因(推測でもOK)
- 対応内容
- 改善アイデア
【実践②】週1回の「問題振り返り会議」
時間:15分程度 参加者:全スタッフ 内容:
- 今週起きた問題の共有
- 解決できた問題の成果報告
- 新しい改善アイデアの募集
【実践③】「問題発見賞」の設置
スタッフが問題を見つけて報告してくれたら、小さな報奨(お菓子や食事券など)を贈る制度を作りましょう。
まとめ:問題は成長の種
問題を避けようとする店は現状維持が精一杯。 問題を歓迎する店は、日々成長し続けます。
問題歓迎店の特徴
- スタッフが積極的に改善提案をする
- 同じ問題が二度と起きない
- お客様からの信頼が厚い
- 競合店との差が日々広がる
- 経営者が安心して店を任せられる
問題回避店の特徴
- 表面的な対処しかしない
- 同じ問題が何度も発生
- スタッフが受け身で成長しない
- お客様満足度が頭打ち
- 経営者が常に不安を抱える
あなたはどちらの店を選びますか?
今日からできる3つのアクション
- 問題収集ノートを作成(所要時間:5分)
- スタッフに「問題歓迎」メッセージを伝達(所要時間:10分)
- 今週の問題振り返り会議の日程決定(所要時間:5分)
明日から、あなたの店に起きる全ての問題が「改善のチャンス」に変わります。
問題を歓迎する文化を作ることで、あなたの店は確実に、そして継続的に成長し続ける店になるでしょう。









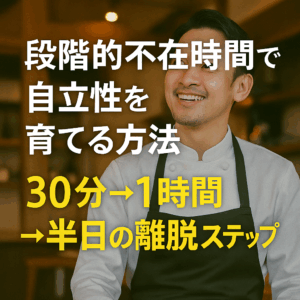
コメント