「また同じ問題が起きた…これって防げなかったのかな?」
毎日のように発生する様々な問題。でも実は、その問題の90%は 「事前に防げる問題」 なのです。
残りの10%だけが 「どうしても起きてしまう問題」 。
この区別ができるようになると、あなたの店舗運営は劇的に変わります。問題が起きてから慌てて対処するのではなく、問題が起きる前に防ぐことができるようになるのです。
今日は、「防げる問題」と「対処すべき問題」を見分ける技術と、それぞれに最適な対策をお教えします。
問題を2つに分類する重要性
分類①:予防可能な問題(約90%)
特徴
- 事前の準備や仕組みで防げる
- 同じパターンで繰り返し発生する
- 人為的なミスが原因のことが多い
- 予測・計画で回避可能
例
- 食材の期限切れ
- 機械の突然の故障
- スタッフの遅刻・欠勤
- 予約のダブルブッキング
- 在庫切れによるメニュー提供不可
分類②:対処必要な問題(約10%)
特徴
- 事前予測が困難または不可能
- 外部要因に左右される
- 完全に防ぐことはできない
- 迅速な対応力が重要
例
- 自然災害(地震・台風)
- お客様の突然の体調不良
- 近隣での事故による交通渋滞
- 仕入れ先の突然の廃業
- 法律・制度の急な変更
「予防可能な問題」の見分け方
見分けポイント①:過去の発生履歴
予防可能な問題の特徴
□ 過去6か月で2回以上発生している
□ 「また同じことが...」と感じる
□ 特定の時期・時間帯に集中して発生
□ 特定の人が関わると発生しやすい
□ 「もう少し早く気づいていれば...」と後悔する
見分けポイント②:原因の所在
予防可能な問題の原因パターン
- 人的要因:注意不足、スキル不足、疲労
- 仕組み要因:チェック体制の不備、マニュアルの不足
- 環境要因:設備の老朽化、在庫管理の不備
- 計画要因:スケジュール調整の甘さ、予測の不足
見分けポイント③:「もし○○していたら」テスト
問題が起きた時に以下の質問をしてみてください:
【予防可能性チェック質問】
・もし事前にチェックしていたら防げた?
・もし準備を十分していたら防げた?
・もし仕組みがあったら防げた?
・もし情報共有ができていたら防げた?
・もし計画を立てていたら防げた?
1つでも「Yes」なら、それは予防可能な問題です。
業種別「予防可能問題」と「対処必要問題」の分類例
【居酒屋】問題分類表
予防可能な問題(事前対策で解決)
【食材管理関連】
❌ 食材の期限切れ → ⭕ 毎日の期限チェックシステム
❌ 仕入れ忘れ → ⭕ 自動発注システム
❌ 在庫切れ → ⭕ 最低在庫量の設定
【スタッフ関連】
❌ シフトの穴 → ⭕ 代替要員システム
❌ 接客ミス → ⭕ 接客マニュアル+研修
❌ レジの打ち間違い → ⭕ ダブルチェック体制
【設備関連】
❌ 機械の突然故障 → ⭕ 定期メンテナンス
❌ 冷蔵庫の温度異常 → ⭕ 温度アラーム設置
❌ ガス切れ → ⭕ 予備ボンベ+定期点検
対処必要な問題(起きてから対応)
【外部要因】
・急な悪天候による客足減少
・近隣での事故による道路封鎖
・仕入れ先の突然の配送トラブル
【お客様要因】
・お客様の急病・けが
・お客様同士のトラブル
・アレルギー症状の発症
【不可抗力】
・停電・断水
・地震・災害
・法改正による急な対応
【美容室】問題分類表
予防可能な問題
【予約管理関連】
❌ ダブルブッキング → ⭕ 予約システムの改善
❌ お客様の遅刻混乱 → ⭕ 前日確認システム
❌ 施術時間の読み違い → ⭕ 標準時間の設定
【技術・サービス関連】
❌ カラー剤の調合ミス → ⭕ チェックリスト導入
❌ 仕上がりの不満 → ⭕ カウンセリング強化
❌ 材料切れ → ⭕ 使用量予測システム
【スタッフ関連】
❌ 技術レベルのバラつき → ⭕ 研修制度の充実
❌ 接客対応の違い → ⭕ 接客マニュアル統一
❌ 新人の早期退職 → ⭕ 育成プログラム改善
対処必要な問題
【お客様要因】
・カラー剤によるアレルギー反応
・施術中の体調不良
・髪質の想定外の反応
【外部要因】
・材料メーカーの製造中止
・近隣工事による騒音
・流行の急激な変化
【カフェ】問題分類表
予防可能な問題
【商品提供関連】
❌ コーヒーの味のブレ → ⭕ 抽出手順の標準化
❌ 注文の聞き間違い → ⭕ 復唱確認システム
❌ 提供時間のバラつき → ⭕ オペレーション改善
【在庫・材料関連】
❌ 人気メニューの材料切れ → ⭕ 需要予測システム
❌ パンの売れ残り → ⭕ 発注量調整システム
❌ 牛乳の期限切れ → ⭕ 先入先出管理
【環境・設備関連】
❌ 席の汚れ → ⭕ 清掃チェックリスト
❌ Wi-Fiの不調 → ⭕ 定期的な機器チェック
❌ 空調の効きすぎ → ⭕ 時間帯別設定
対処必要な問題
【お客様要因】
・お客様の体調急変
・お客様同士のトラブル
・支払いトラブル
【外部要因】
・電力会社の計画停電
・水道工事による断水
・配送業者のストライキ
予防システム構築の実践手順
STEP1:問題履歴の分析
過去1年間の問題を全てリストアップ
【記録項目】
日付:
問題内容:
原因:
対応時間:
影響範囲:
再発の有無:
予防可能性:可能/不可能
予防方法案:
STEP2:予防可能問題の優先順位付け
優先順位決定基準
【高優先度】
・発生頻度が高い(月1回以上)
・影響が大きい(売上・顧客満足度に直結)
・予防コストが低い
【中優先度】
・発生頻度は中程度(3か月に1回程度)
・影響は中程度
・予防コストは中程度
【低優先度】
・発生頻度が低い(年1回未満)
・影響は限定的
・予防コストが高い
STEP3:予防システムの設計
システム設計の4要素
①チェックシステム
【日次チェック】
・食材期限、機器動作、清掃状況
【週次チェック】
・在庫量、スタッフスケジュール、設備点検
【月次チェック】
・売上分析、顧客満足度、スタッフ評価
【年次チェック】
・設備更新、契約見直し、保険確認
②早期警告システム
【アラート設定】
・在庫が最低量を下回った時
・機器の異常値を検知した時
・予約が集中した時
・スタッフの体調不良が続いた時
③バックアップシステム
【代替手段の準備】
・主要機器の予備
・代替メニューの準備
・代替スタッフの確保
・代替仕入先の開拓
④自動化システム
【自動化対象】
・発注処理
・予約確認
・温度管理
・清掃スケジュール
STEP4:対処システムの準備
予防できない10%の問題に対しては、迅速で的確な対処システムを準備します。
対処システムの要素
【即座対応】
・緊急連絡先リスト
・応急処置マニュアル
・代替案の準備
【短期対応】
・専門家への相談ルート
・保険・補償制度の活用
・お客様への説明・謝罪
【中長期対応】
・根本的な改善策の検討
・再発防止策の実施
・システム全体の見直し
効果的な予防システムの運用方法
運用ポイント①:「予防の日」を設定
月1回の予防点検日
【点検内容】
・予防システムの動作確認
・チェックリストの見直し
・新たな予防可能問題の発見
・予防システムの改善提案
運用ポイント②:予防成果の可視化
予防効果測定指標
【定量指標】
・問題発生回数の変化
・対応時間の短縮
・お客様クレーム数の減少
・売上ロスの軽減
【定性指標】
・スタッフの安心感向上
・お客様満足度の向上
・経営者の精神的負担軽減
運用ポイント③:継続改善のサイクル
PDCA サイクルの運用
【Plan(計画)】
・予防システムの設計
・年間予防計画の策定
【Do(実行)】
・日々の予防活動実施
・チェックリストの実行
【Check(確認)】
・予防効果の測定
・問題発生状況の分析
【Action(改善)】
・システムの修正・改善
・新たな予防策の追加
よくある予防システム構築の失敗パターン
失敗①:完璧を求めすぎる
問題:100%の予防を目指して複雑なシステムを作り、運用が困難になる
対策:
- まずは80%の予防効果を目指す
- シンプルで継続可能なシステムから始める
- 段階的に改善していく
失敗②:予防コストを軽視する
問題:予防にかかるコストを考慮せず、非現実的なシステムを設計
対策:
- 予防コストと問題発生コストを比較
- ROI(投資対効果)を計算
- 優先順位を明確にする
失敗③:スタッフの協力を得られない
問題:「面倒くさい」「今まで通りでいい」という抵抗
対策:
- 予防の効果・メリットを具体的に説明
- スタッフの意見を取り入れたシステム設計
- 小さな成功体験から始める
今すぐできる実践チェックリスト
【今日実施】問題の分類作業
□ 過去3か月の問題をリストアップ □ 各問題を「予防可能」「対処必要」に分類 □ 予防可能問題を頻度・影響度で優先順位付け □ 最優先問題1つの予防策を検討
【今週実施】予防システムの設計
□ 最優先問題の予防システム設計 □ 必要なツール・仕組みの洗い出し □ 実施スケジュールの作成 □ スタッフへの説明・協力要請
【今月実施】システムの本格運用
□ 予防システムの試験運用開始 □ 効果測定方法の確立 □ 問題点の洗い出しと改善 □ 次の優先問題への着手
まとめ:「問題対応型経営」から「問題予防型経営」への転換
問題が起きてから慌てて対処する経営者と、問題を事前に防ぐ経営者。その違いは「問題の分類能力」にあります。
問題対応型経営の特徴
- 毎日が「火消し」作業
- 同じ問題が何度も発生
- スタッフが疲弊している
- お客様への影響が大きい
- 経営者が常に不安
問題予防型経営の特徴
- 問題発生前に対策済み
- 同じ問題の再発が激減
- スタッフが安心して働ける
- お客様満足度が安定
- 経営者が戦略業務に集中
今日から始める3つのアクション
- 過去3か月の問題分類作業(所要時間:30分)
- 最優先予防対象の決定(所要時間:15分)
- 1つの予防システム設計開始(所要时间:1時間)
3か月後、あなたの店では「また同じ問題が…」という言葉が大幅に減っているでしょう。
そして1年後には、「あの店はいつも安定している」とお客様から信頼される店になっているはずです。
問題は「起きてから対処する」ものではなく「起きる前に防ぐ」もの。
この発想の転換が、あなたの店舗経営を根本から変えてくれるでしょう。
今すぐ問題の分類作業を始めて、「問題予防型経営」への第一歩を踏み出しましょう!









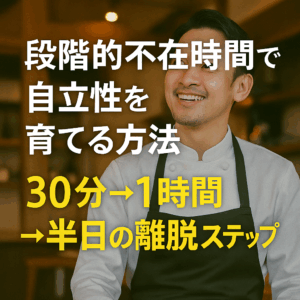
コメント