「社長、これってどうしたらいいですか?」
1日に何回この言葉を聞きますか?10回?20回?もしかして数えきれないほど?
そのたびに手を止めて説明し、気がつけば自分の仕事が全然進まない…そんな毎日を送っていませんか?
実は、スタッフからの質問攻めは 「判断基準が曖昧だから」 起きているのです。
今日は、スタッフが自分で判断できるようになる「魔法の判断基準」の作り方をお教えします。
なぜスタッフは何でも聞いてくるのか?
根本原因:「正解」が分からない不安
スタッフの心理を理解してみましょう:
【スタッフの心の声】
「自分で判断して間違えたら怒られる...」
「前に似たような件で注意された...」
「どこまでが自分の権限なのか分からない...」
「失敗するくらいなら聞いた方が安全...」
つまり、「聞いてくる」のは「怠けている」からではなく「不安」だからなのです。
よくある曖昧な指示の例
経営者は良かれと思って次のような指示を出しますが、これが混乱の原因です:
❌ 曖昧な指示例
- 「臨機応変に対応して」
- 「お客様の立場になって考えて」
- 「常識的に判断して」
- 「適切に処理して」
- 「いい感じでお願いします」
スタッフにとってこれらは「正解が分からない指示」 なのです。
効果的な判断基準の3つの要素
要素①:具体的な数値基準
抽象的な表現を具体的な数値に変換します。
変換例
❌「高額な商品は慎重に」
⭕「10,000円以上の商品は店長確認必須」
❌「お客様をお待たせしないように」
⭕「お客様の待ち時間が5分を超える場合は説明とお詫び」
❌「適度に声をかけて」
⭕「お客様が入店から3分経ったら必ず声かけ」
要素②:段階別の対応基準
問題の大きさに応じた対応レベルを設定します。
段階別対応例:クレーム対応
【レベル1:軽微なクレーム】
・商品の温度、味の好み等
→ 現場スタッフが即座に対応・解決
【レベル2:中程度のクレーム】
・サービスの不備、待ち時間のお叱り等
→ 責任者が対応、必要に応じて割引等
【レベル3:重大なクレーム】
・食中毒疑い、大声での抗議、SNS拡散の恐れ等
→ 店長・経営者が直接対応
要素③:判断フローチャート
「もし○○なら△△、そうでなければ□□」という形で判断の道筋を示します。
判断フローチャート例:返品対応
お客様から返品要請
↓
商品に問題がある?
YES → 即座に返金・交換
NO ↓
購入から7日以内?
YES → お客様都合での返品受付
NO ↓
特別な事情がある?
YES → 責任者判断
NO → 丁寧にお断り
業種別「判断基準」作成実例
【居酒屋】の判断基準システム
① 料金関連の判断基準
【割引・サービス提供基準】
・1,000円以下:スタッフ判断でOK
・1,001円〜5,000円:主任以上の判断
・5,001円以上:店長判断必須
【無料サービス提供基準】
・ドリンク1杯:待ち時間10分超過時
・前菜サービス:注文ミス発生時
・デザートサービス:誕生日・記念日のお客様
② 接客対応の判断基準
【お客様からの特別要望】
・メニューの辛さ調整:全スタッフ対応可
・食材の変更(アレルギー等):調理場確認後対応
・大幅な調理法変更:お断り(代替案提示)
・持ち込み:原則お断り(要相談の場合は店長へ)
【美容室】の判断基準システム
① 施術関連の判断基準
【カラー・パーマの判断基準】
・前回と同じ施術:スタイリスト判断でOK
・大幅なイメージチェンジ:カウンセリング必須
・ハイダメージ毛への施術:トップスタイリスト判断
・妊娠中のお客様:施術内容に制限あり
② 予約調整の判断基準
【予約変更対応基準】
・30分以内の変更:受付スタッフ判断でOK
・当日キャンセル:キャンセル料説明後受付
・no-show(無断キャンセル):次回予約時に確認
・頻繁な変更客:店長相談
【カフェ】の判断基準システム
① 商品提供の判断基準
【ミス対応基準】
・注文と違う商品を提供:即座に正しい商品提供
・お客様都合の変更:差額をいただいて対応
・当店ミスによる作り直し:無料で対応+お詫び品
・温度に関するクレーム:作り直し無料
② カスタマイズ対応基準
【メニューカスタマイズ】
・ドリンクの甘さ調整:無料対応
・ミルクの種類変更:50円追加で対応
・食材追加:メニュー表記の追加料金
・大幅な内容変更:お断り(近いメニュー提案)
判断基準作成の実践5ステップ
STEP1:質問内容の分類・整理
まず1週間、スタッフからの質問を全て記録します。
質問記録フォーマット
日時:
質問者:
質問内容:
あなたの回答:
質問の分類:(接客・会計・商品・クレーム・その他)
緊急度:(高・中・低)
STEP2:頻出質問TOP10を特定
記録した質問を分析し、最も多い質問から優先的に基準を作ります。
分析項目
- 最も多い質問は?
- 同じ人から何度も出る質問は?
- 時間帯による傾向は?
- 経験年数による違いは?
STEP3:基準を3段階で設定
各質問に対して、明確な判断基準を設定します。
3段階設定例
【段階1:全員が判断可能】
→ 新人でも迷わず判断できるレベル
【段階2:経験者が判断可能】
→ 6か月以上の経験者なら判断できるレベル
【段階3:責任者判断必要】
→ 店長・マネージャーレベルの判断が必要
STEP4:フローチャート化
複雑な判断は、誰でも同じ結論に達するフローチャートにします。
フローチャート作成のコツ
- YES/NOで答えられる質問にする
- 最大3ステップまでに収める
- 最後は必ず具体的な行動指示で終わる
- 例外パターンも含める
STEP5:テスト運用と改善
作成した判断基準を実際に使ってもらい、問題点を修正します。
テスト運用のポイント
- 1週間のテスト期間を設定
- 使いにくい点を遠慮なく報告してもらう
- 実際の事例で基準が機能するかチェック
- 必要に応じて基準を修正
判断基準を定着させる「教育システム」
①ロールプレイング訓練
月1回の判断力向上訓練
【訓練内容】
・実際のケースを想定したロールプレイ
・判断基準を見ながらの実践練習
・間違いやすいポイントの共有
・新しいケースの判断基準追加
②「判断基準カード」の配布
持ち運べるサイズのカードに要点をまとめます。
カードの内容例
【緊急時判断基準カード】
・1,000円以下 → 自分で判断
・5,000円以下 → 主任相談
・5,000円超 → 店長相談
・お客様のお怒り → まず謝罪・傾聴
・機械故障 → 使用中止・店長連絡
③成功事例の共有
週1回の判断事例共有会
【共有内容】
・今週の良い判断事例
・迷った時の考え方
・お客様から褒められた対応
・改善すべき判断の反省
よくある失敗パターンと対策
失敗①:基準が複雑すぎる
問題:完璧を求めて複雑な基準を作り、誰も使えない
対策:まずは80%のケースを解決できるシンプルな基準から始める
失敗②:例外パターンを考慮しない
問題:基準外のケースが発生すると結局質問される
対策:「その他の場合は○○に相談」という逃げ道を用意
失敗③:基準の存在を忘れられる
問題:基準を作ったが、いつの間にか使われなくなる
対策:
- 目に見える場所に掲示
- 定期的な確認会議
- 新人研修に必ず組み込む
「自立型スタッフ」育成の効果測定
測定指標①:質問回数の変化
【月次測定】
・スタッフからの質問回数
・質問の種類(単純/複雑)
・同じ質問の反復回数
・質問者の変化
測定指標②:判断の正確性
【正確性チェック】
・自主判断の成功率
・お客様満足度の変化
・クレーム発生率
・売上への影響
測定指標③:スタッフの自信度
【定性評価】
・「自分で判断できる」と感じるスキル項目数
・仕事への積極性の変化
・責任感の向上度
・チーム内での発言の変化
今すぐできる実践アクション
【今日から1週間】質問ログの記録
□ 質問記録用紙を準備 □ スタッフからの質問を全て記録 □ 自分の回答も合わせて記録 □ 1日の記録時間(5分程度)を確保
【来週実施】頻出質問の分析
□ 記録した質問をカテゴリー別に分類 □ 頻出TOP5を特定 □ 各質問の判断基準案を作成 □ スタッフに判断基準案を相談
【来月完成】判断基準システム
□ 最終版の判断基準を完成 □ 全スタッフへの説明・研修実施 □ 判断基準カードの作成・配布 □ 1か月後の効果測定実施
まとめ:「質問される経営者」から「頼られる経営者」へ
スタッフからの質問に忙殺される経営者と、スタッフが自立して動く店を持つ経営者。その違いは「明確な判断基準があるかどうか」です。
質問攻めの店の特徴
- 社長が常に忙しそう
- スタッフが受け身で指示待ち
- 同じ質問が何度も繰り返される
- 経営者が現場を離れられない
自立型スタッフの店の特徴
- スタッフが積極的に判断・行動
- 社長は戦略的な仕事に集中
- 問題が起きてもスムーズに解決
- チーム全体のレベルが高い
今日から始める3つのアクション
- 質問ログの記録開始(所要時間:1日5分)
- 昨日までの頻出質問TOP3をリストアップ(所要時間:10分)
- 1つの質問に対する判断基準を作成(所要時間:15分)
1週間後、あなたへの質問回数は確実に減り始めます。
1か月後には、スタッフから「こう判断しました」という報告が増え、あなたは本来の経営者業務に集中できるようになるでしょう。
明確な判断基準は、スタッフの成長を促し、あなたの時間を創出する最強のツールです。
今すぐ判断基準作りを始めて、「質問される経営者」から「頼られる経営者」への転換を図りましょう!









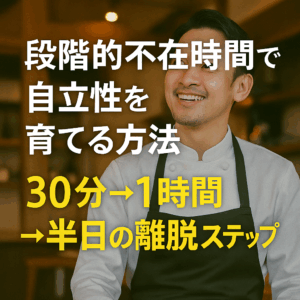
コメント