やることを増やす人が絶対に成功しない理由
「競合店が新しいサービスを始めたから、うちも負けずに何か追加しなきゃ…」 「お客さんのために、もっといろんなメニューを用意した方がいいかな…」 「売上が伸び悩んでいるから、新しい取り組みを増やそう…」
売上や成果が思うように出ない時、こんな風に「もっと何かを追加しよう」と考えることはありませんか?
実は、これこそが多くの経営者を失敗に導く 「やることを増やす病」 なのです。まるで穴の開いたバケツに水を注ぎ続けるようなもので、いくら頑張っても水は溜まらず、最終的にはバケツごと壊れてしまいます。
失敗する経営者と成功する経営者の最大の違いは、問題が起きた時の対処法にあります。失敗する人は「足し算」で解決しようとし、成功する人は「引き算」で本質に迫ります。まるで熟練の医師が症状に薬を重ねるのではなく、根本原因を特定して的確に治療するように、問題の核心を見抜いて解決するのです。
やることを増やす思考の危険性を理解することで、あなたは無駄な努力の泥沼から抜け出し、確実に成果を生み出す経営者になることができます。
この記事では、飲食店・美容室経営者でも今すぐ理解できる「やることを増やす人が絶対に成功しない理由」を、具体的な失敗事例とともに分かりやすく解説します。
「やることを増やす病」の5つの症状
症状1:問題のすり替え現象
本当の問題から目をそらす逃避行動
問題すり替えのメカニズム:
本当の問題:「既存サービスの品質が低い」
↓
すり替え思考:「サービスの種類が少ないからだ」
↓
間違った解決策:「新しいサービスを追加しよう」
↓
結果:根本問題は未解決、新たな問題が追加
すり替えの典型パターン:
【売上不振の時】
本当の問題 → すり替え思考 → 間違った対策
・味が劣る → メニューが少ない → 新メニュー追加
・接客が悪い → サービスが少ない → 新サービス追加
・立地が悪い → 営業時間が短い → 営業時間延長
・価格が高い → 付加価値が少ない → オプション追加
・専門性なし → 幅広さが足りない → 事業領域拡大
実例:定食屋「味の家」の問題すり替え地獄
【最初の問題】
お客さんからの苦情:「味が薄い」「料理が冷めている」
本当の問題:調理技術と提供スピードの不足
【1年目の間違った対策】
すり替え思考:「メニューが少ないから選択肢がない」
間違った対策:丼もの10種類追加
結果:調理が更に複雑になり、味も提供速度も悪化
【2年目の更なる間違い】
すり替え思考:「和食だけでは物足りない」
間違った対策:洋食メニュー8種類追加
結果:「何の店かわからない」状態、品質更に低下
【3年目の致命的判断】
すり替え思考:「サービスが足りない」
間違った対策:宅配、ケータリング、弁当販売開始
結果:完全にキャパオーバー、お客さん大幅減少
【3年後の悲惨な状況】
・メニュー数:12種類→45種類
・サービス種類:1種類→4種類
・売上:月180万円→月120万円(35%減少)
・利益:月40万円→赤字月15万円
・お客さん満足度:「何もかも中途半端」
・スタッフ:疲労困憊で全員退職
・経営者:「こんなに頑張っているのになぜ?」と困惑
根本問題の「調理技術と提供速度」は3年間一度も改善されず
症状2:リソース限界の無視
有限のリソースを無限に分散させる錯覚
リソース分散の現実:
【基本的事実】
・時間:1日24時間(変更不可)
・体力:人間の限界がある(変更不可)
・お金:売上から必要経費を差し引いた分のみ(有限)
・集中力:マルチタスクで激減(科学的事実)
・スタッフ:雇用可能数に限界(経済的制約)
【やることを増やす人の錯覚】
・「時間は作れる」(無理)
・「頑張れば何でもできる」(身体的に無理)
・「投資すれば回収できる」(リスク無視)
・「同時にやれば効率的」(科学的に間違い)
・「人を増やせば解決」(教育コスト無視)
実例:美容室「Total Beauty」の限界突破失敗
【リソース計算を無視した拡大】
1年目:基本サービス
・カット、カラー、パーマ
・営業時間:10時間
・スタッフ:3人
・技術習得時間:月50時間
・お客さん1人あたり時間:90分
・1日対応可能客数:20人
2年目:ネイル・エステ追加
・必要な技術習得時間:月100時間(2倍)
・新設備投資:300万円
・お客さん1人あたり時間:150分(1.7倍)
・1日対応可能客数:12人(40%減少)
3年目:着付け・写真撮影追加
・必要な技術習得時間:月150時間(3倍)
・新設備投資:累計600万円
・お客さん1人あたり時間:210分(2.3倍)
・1日対応可能客数:8人(60%減少)
4年目:ブライダル・企画業務追加
・必要な技術習得時間:月200時間(4倍)
・新設備投資:累計1000万円
・お客さん1人あたり時間:300分(3.3倍)
・1日対応可能客数:5人(75%減少)
【リソース限界突破の結果】
・スタッフの技術レベル:すべて中途半端
・お客さん待ち時間:30分→2時間
・予約の取りやすさ:当日可→2ヶ月待ち
・スタッフの疲労度:限界を超え、2人退職
・品質満足度:「器用貧乏」の評価
・設備投資の回収:全く見込めず
・経営者の睡眠時間:8時間→4時間(健康悪化)
・家族関係:「仕事ばかりで家族を見ない」
・売上:増加
・利益:大幅減少(設備費・人件費・教育費で消失)
症状3:品質希釈の法則
サービス増加に反比例する品質低下
品質希釈の科学的根拠:
【集中の法則】
・1つのことに100%集中 → 100%の品質
・2つのことに分散 → 各50%の品質
・3つのことに分散 → 各33%の品質
・10つのことに分散 → 各10%の品質
【学習曲線の法則】
・同じことを1000回 → 専門家レベル
・10のことを各100回 → 初心者レベル
【記憶の法則】
・1つの技術 → 完全記憶・自動化
・10の技術 → 記憶曖昧・ミス多発
実例:カフェ「All in One」の品質崩壊
【専門カフェ時代(開業1年目)】
・コーヒー5種類のみ
・自家焙煎による品質へのこだわり
・1杯1杯丁寧な抽出
・お客さんの評価:「○○で最も美味しいコーヒー」
・リピート率:85%
・口コミ:「コーヒー好きなら絶対行くべき」
【拡大期(2年目):軽食追加】
・サンドイッチ、パスタ、ケーキ追加
・コーヒーへの集中時間:80%→50%
・お客さんの評価:「コーヒーは美味しいけど、料理は普通」
・リピート率:85%→70%
【更なる拡大(3年目):ディナー開始】
・ステーキ、魚料理、コース料理追加
・コーヒーへの集中時間:50%→20%
・焙煎:自家製→業者仕入れに変更(時間不足)
・お客さんの評価:「何でもあるけど、何も美味しくない」
・リピート率:70%→40%
【迷走期(4年目):宴会・ケータリング】
・宴会場機能、ケータリングサービス開始
・コーヒーへの集中時間:20%→5%
・お客さんの評価:「昔は美味しかったのに...」
・リピート率:40%→20%
・新規客:「期待して来たけどガッカリ」
【崩壊期(5年目):品質の完全希釈】
・コーヒー:「普通の店で飲める味」
・料理:「チェーン店以下の品質」
・サービス:「注文してから30分待ち」
・従来のコーヒー愛好家:完全に離脱
・「コーヒーの美味しいカフェ」→「何でもあるファミレス」
・売上:増加したものの
・利益:人件費・設備費で消失
・ブランド価値:完全に失墜
症状4:選択麻痺による売上低下
選択肢過多がお客さんの決定を阻害
選択麻痺の心理学:
【ジャムの実験(有名な心理学実験)】
・24種類のジャム試食コーナー → 立ち寄り率60%、購入率3%
・6種類のジャム試食コーナー → 立ち寄り率40%、購入率30%
結論:選択肢が多すぎると、人は選択をあきらめる
【レストランメニューの研究】
・10品以下 → 注文まで平均5分、満足度高
・20品程度 → 注文まで平均8分、満足度中
・30品以上 → 注文まで平均15分、満足度低
・50品以上 → 注文決まらず退店が20%
実例:ラーメン店「麺王国」の選択麻痺地獄
【拡大の歴史】
1年目:醤油、味噌、塩の3種類
→ 注文スムーズ、回転率良好
2年目:つけ麺、油そば追加で8種類
→ やや迷うが許容範囲
3年目:地域限定、季節限定で15種類
→ 注文に時間がかかり始める
4年目:辛さ調整、麺の硬さ、トッピングで50通り
→ お客さんの混乱が顕著に
5年目:「何でも作ります」で選択肢無限
→ 完全な麻痺状態
【5年目の悲惨な状況】
・メニュー表:A3用紙4枚(読むのに10分)
・注文時間:平均15分(以前は1分)
・「何がオススメですか?」質問:80%のお客さん
・注文変更・キャンセル:30%
・「決められないから帰る」客:15%
・厨房の混乱:毎回レシピ確認が必要
・調理ミス:週に5回以上
・お客さん満足度:「迷って疲れる」
・回転率:1.5倍→0.7倍(半分以下)
・「美味しいラーメン店」→「迷子になる店」の評判
症状5:コスト感覚の麻痺
追加コストを軽視する危険な思考
コスト麻痺のパターン:
【見た目のコスト】新メニュー1品追加
・材料費:月1万円
・「安いじゃないか」
【隠れたコスト】実際の負担
・材料仕入れ時間:月5時間
・調理練習時間:月10時間
・在庫管理時間:月3時間
・レシピ管理時間:月2時間
・発注業務時間:月2時間
・廃棄ロス:月5千円
・時給3000円換算:月6.6万円
・実際のコスト:月7.1万円(7倍!)
実例:定食屋「何でも食堂」のコスト地獄
【1品ずつ追加の軽い気持ち】
「お客さんの要望に応えよう」
「1品追加するだけなら簡単」
「材料費も安いし」
「すぐできそう」
【5年間の累積追加コスト】
1年目:基本定食10品
2年目:丼もの5品追加
3年目:麺類6品追加
4年目:洋食8品追加
5年目:中華7品追加
総メニュー数:36品
【見た目の材料費】
基本:月10万円
追加分:月12万円
合計:月22万円(2.2倍)
【実際の総コスト】
・材料費:月22万円
・仕入れ時間コスト:月18万円
・調理習得コスト:月25万円
・在庫管理コスト:月8万円
・廃棄ロスコスト:月6万円
・ミス対応コスト:月4万円
・メニュー管理コスト:月3万円
合計:月86万円(8.6倍!)
売上増加:月50万円
実質赤字:月36万円
成功する人が実践する「やらない勇気」
勇気1:機会損失を恐れない強さ
「やらないことで失うもの」より「やることで失うもの」を重視
機会損失の正しい理解:
【間違った思考】
「これをやらなかったら、お客さんを逃すかも」
「競合がやっているから、やらないと負ける」
「チャンスを逃すともったいない」
【正しい思考】
「これをやったら、本業がおろそかになる」
「競合と同じことをしても差別化できない」
「チャンスに見えるものの90%は罠」
機会損失vs集中利益の比較:
【やらないことで失う売上】10万円/月
vs
【やることで失う利益】
・本業品質低下による売上減:30万円/月
・追加コスト:20万円/月
・機会コスト:15万円/月
合計:65万円/月
実質的損失:55万円/月
勇気2:お客さんの「全て」に応えない覚悟
顧客満足≠顧客要望の全受容
正しい顧客満足の考え方:
【間違った考え】
・お客さんの要望は全て聞くべき
・断るとお客さんが離れる
・サービスは多い方が良い
【正しい考え】
・お客さんの本当のニーズを見極める
・専門性の方が顧客満足度は高い
・選択の負担を減らすのもサービス
実例:寿司屋「一心」の断る勇気
【お客さんからの様々な要望】
「ラーメンもメニューに入れて」
「焼肉もできるようにして」
「ピザも作れない?」
「子ども向けのメニューが欲しい」
「デザートも充実させて」
【大将の判断】
「うちは寿司屋です。寿司で勝負します」
全ての要望を丁寧に断り、寿司の品質向上に集中
【5年後の結果】
・「○○で最も美味しい寿司屋」として確立
・客単価:3倍向上
・予約:1ヶ月待ち
・お客さん満足度:最高レベル
・「寿司ならここ」の絶対的地位
・要望を断られたお客さんも「専門性が高くて良い」と評価
勇気3:競合の真似をしない独自性
差別化は足し算ではなく引き算から
競合対応の間違いパターン:
競合A:メニュー30品 → うちは40品にしよう
競合B:営業時間12時間 → うちは14時間にしよう
競合C:サービス10種類 → うちは15種類にしよう
結果:競合の劣化コピーになる
正しい差別化アプローチ:
競合がやっていることはあえてやらない
→ 空いているポジションで専門性を確立
→ 唯一無二の存在になる
「やることを増やす病」からの脱却法
脱却法1:現在のやることリストの全見直し
すべてのサービス・商品・活動の損益分析
見直しの手順:
1. 現在やっていることを全てリストアップ
2. それぞれの売上・利益・時間コストを計算
3. お客さん満足度・リピート率を調査
4. 競合優位性・専門性への貢献度を評価
5. 総合評価による優先順位付け
脱却法2:やめる基準の明確化
客観的な判断基準による決断
やめる基準:
・利益率が平均以下
・時間対効果が悪い
・専門性を薄める
・お客さんのニーズが低い
・競合優位性がない
・品質維持が困難
・本業に悪影響
脱却法3:段階的な縮小・撤退
急激な変化を避けた計画的な整理
段階的縮小の手順:
【第1段階】明らかに不要なものの即時停止
【第2段階】効果の薄いものの段階的縮小
【第3段階】重複するもののどちらかを選択
【第4段階】残したもののクオリティ向上
【第5段階】専門性の確立と差別化
脱却法4:集中分野の品質向上
リソースを集中投下して圧倒的差別化
集中投下の効果:
・技術レベルの飛躍的向上
・効率性の大幅改善
・お客さん満足度の向上
・競合との明確な差別化
・利益率の改善
・ブランド価値の確立
まとめ:やらない勇気が真の成功を生む
やることを増やす思考は、短期的には成長に見えて、長期的には確実に失敗に導く危険な罠です。
「やることを増やす病」の5つの症状:
- 問題のすり替え現象 – 本当の問題から目をそらす逃避行動
- リソース限界の無視 – 有限のリソースを無限に分散させる錯覚
- 品質希釈の法則 – サービス増加に反比例する品質低下
- 選択麻痺による売上低下 – 選択肢過多がお客さんの決定を阻害
- コスト感覚の麻痺 – 追加コストを軽視する危険な思考
成功する人が実践する「やらない勇気」:
- 機会損失を恐れない強さ
- お客さんの「全て」に応えない覚悟
- 競合の真似をしない独自性
脱却のための4つの方法:
- 現在のやることリストの全見直し
- やめる基準の明確化
- 段階的な縮小・撤退
- 集中分野の品質向上
実践のポイント:
- 問題が起きても安易に足し算で解決しようとしない
- リソースの限界を正しく認識して現実的な判断をする
- 品質と専門性を最優先に考える
- お客さんの選択負担を減らすことを重視する
- 隠れたコストまで含めた正確な損益計算をする
今日から始められること: まずは現在やっていることを全てリストアップし、「これは本当に必要か?」「これは利益を生んでいるか?」「これは専門性を高めているか?」を一つずつ問いかけてみてください。
やることを増やす病から脱却することで、あなたは「忙しいのに成果が出ない」状態から抜け出し、「効率的に高い成果を生み出す」真の成功者になることができます。「何を加えるか」ではなく「何を手放すか」を考える勇気が、あなたの経営を劇的に変えるのです。
今日のアクション: 今すぐ以下の「やることを増やす病」診断を実行してください:
- やることリスト作成:現在のすべてのサービス・商品・活動を書き出す
- 5症状チェック:問題すり替え・リソース無視・品質希釈・選択麻痺・コスト麻痺の症状がないか確認
- 損益分析:各項目の本当の利益(隠れコスト含む)を計算
- やめる候補特定:明らかに不要・低効果なもの3つを選択
- 第1歩実行:最も不要なもの1つを今日からやめる決断
- 集中分野決定:残ったリソースを集中投下する分野を1つ決定
あなたの「やらない勇気」が、今日から無駄の排除と専門性の確立による真の成功への道筋を作り始めます。


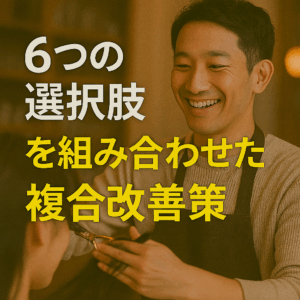






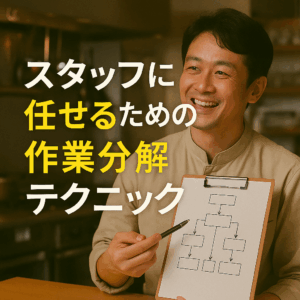
コメント