「今の延長線上」で結果を変えようとする人の落とし穴
今日は、ジョイ婦人とジョイ子が浜松の実家に帰省。
私は午前中にキックボクシングジムに行きまして、10月に試合に出ることが決まりました。
人生で二度目のキックボクシングの試合。
昨年11月末のほろ苦い初戦デビューでしたが、今回は、勝てたら嬉しいです。
10月は横浜マラソンとキックボクシングの試合と続けてあるので、アグレッシブな月になりそうですが、チャレンジを楽しみたいと思います。
そして、10月のキックボクシングの試合は豊橋の会場なので、愛知の方は、ぜひ、応援しにきてください。
ということで、今日も張り切ってお届けします。
「もう少し頑張れば売上が上がるはず」
「今のやり方をちょっと改善すれば大丈夫」
「あと少しだけ努力すれば結果が出る」
このような考えで、現在の延長線上で結果を変えようとしていませんか?実は、これが多くの人が陥る最大の落とし穴なのです。
今の延長線上の努力では、根本的な結果の変化は得られません。この記事では、なぜ延長線上思考が危険なのか、そして真の変化を起こすために必要な思考転換について解説します。
延長線上思考の典型例
パターン1:量的拡大思考
「今の1.5倍頑張れば1.5倍の結果が出る」
- チラシの配布枚数を1.5倍にする
- 営業時間を1.5倍に延ばす
- スタッフの労働時間を1.5倍にする
- 広告費を1.5倍にかける
パターン2:微調整思考
「少しずつ改善していけば大きな変化が起こる」
- メニューを少し増やす
- 価格を少し下げる
- サービスを少し改善する
- 店内を少し模様替えする
パターン3:努力強化思考
「もっと一生懸命やれば結果が変わる」
- より早く、より長時間働く
- より丁寧に、より完璧にやる
- より多くの業務をこなす
- より安い価格で提供する
なぜ延長線上では結果が変わらないのか
1. 根本的な仕組みが同じ
今のやり方の延長線上にある改善は、基本的な仕組みは何も変わっていません。
具体例:客数が少ない飲食店の場合
延長線上の対策:
- チラシを2倍配る → 配布コストが2倍になるだけ
- 営業時間を延ばす → 光熱費と人件費が増えるだけ
- メニューを増やす → 仕込み時間と食材ロスが増えるだけ
根本的な問題(なぜ客数が少ないのか)は解決されていません。
2. 効率の限界がある
どんなに効率を上げても、現在のやり方には必ず上限があります。
- 1日の労働時間には24時間という物理的限界
- 人間の集中力には生理的限界
- 市場規模には構造的限界
- 価格競争には採算性の限界
延長線上の努力は、これらの限界にぶつかった時点で停止します。
3. 競合との差別化ができない
延長線上の改善は、競合他社でも容易に真似できます。
- 価格を下げる → 競合も下げる
- 営業時間を延ばす → 競合も延ばす
- サービスを少し改善 → 競合も改善する
結果として、業界全体の消耗戦に巻き込まれ、誰も利益を得られない状況に陥ります。
延長線上思考が生まれる心理的要因
1. 変化への恐怖
人間は本能的に大きな変化を恐れます。
- 「今までのやり方を変えるのは怖い」
- 「失敗したらどうしよう」
- 「お客さんが離れるかもしれない」
この恐怖が、安全に見える延長線上の改善に走らせるのです。
2. 沈没コスト効果
これまでの投資や努力を無駄にしたくない心理が働きます。
- 「せっかく今のやり方を覚えたのに」
- 「これまでの投資を無駄にしたくない」
- 「もう少し続ければ結果が出るはず」
3. 現状維持バイアス
現状を維持することが最も安全だと錯覚します。
- 「今のお客さんを失いたくない」
- 「安定している今を変える必要はない」
- 「リスクを取りたくない」
真の変化を起こす「非連続な改善」
延長線上ではない、非連続な改善こそが劇的な結果の変化をもたらします。
例1:QB HOUSE の革命
従来の理髪店の延長線上思考:
- サービスを少し改善する
- 価格を少し下げる
- 営業時間を少し延ばす
- 店舗を少し綺麗にする
QB HOUSE の非連続改善:
- シャンプー・ひげ剃りを完全廃止
- カット10分・1000円の革命的システム
- 立地戦略の根本的変更(駅ナカ展開)
- 全く新しい顧客層の開拓
結果:業界の常識を覆し、急成長を実現
例2:スターバックスの革命
従来の喫茶店の延長線上思考:
- コーヒーの味を少し改善
- 価格を少し下げる
- メニューを少し増やす
- 店内を少し改装
スターバックスの非連続改善:
- 「第三の場所」という新概念の提案
- コーヒー文化そのものの再定義
- 体験価値の徹底的な重視
- 全く新しいライフスタイルの提案
結果:喫茶店市場を超越した新市場を創造
非連続改善を実現する5つのステップ
ステップ1:根本的な問題の特定
表面的な症状ではなく、根本的な問題を特定します。
悪い例: 売上が少ない 良い例: お客様が当店を選ぶ明確な理由がない
悪い例: スタッフが定着しない
良い例: スタッフが成長・やりがいを感じられない職場環境
ステップ2:業界の常識を疑う
「当たり前」とされていることを根本から疑います。
質問例:
- なぜこの業界はこのやり方が普通なのか?
- お客様は本当にこれを求めているのか?
- この常識は誰が決めたのか?
- 他の業界ではどうやっているのか?
ステップ3:顧客価値の再定義
お客様が本当に求めている価値を再定義します。
従来の価値 → 新しい価値
- 安い商品 → 高い体験価値
- 多くの選択肢 → 迷わない最適解
- 丁寧なサービス → 効率的な問題解決
- 高品質な商品 → ライフスタイルの提案
ステップ4:システムの根本設計
延長線上ではない、全く新しいシステムを設計します。
要素:
- 新しい価値提案
- 新しいオペレーション
- 新しい顧客体験
- 新しい収益モデル
ステップ5:小さく始めて大きく育てる
いきなり大きく変えるのではなく、小さくテストして改善を重ねます。
- 限定メニューでのテスト
- 特定曜日・時間帯でのテスト
- 一部顧客向けのテスト
- 段階的な拡大実施
実践ワーク:非連続改善の発想法
ワーク1:常識破りの質問
あなたの業界について、以下の質問を考えてみてください:
- なぜこの業界は◯◯を当たり前だと思っているのか?
- もしこの常識がなかったら、どんなサービスが可能か?
- 全く違う業界のやり方を取り入れたらどうなるか?
- お客様の真のニーズは、今提供しているものと同じか?
ワーク2:価値の再定義
現在提供している価値を根本から見直してみてください:
現在の価値:(例)美味しい料理を提供 新しい価値候補:
- 特別な体験・思い出の提供
- 健康・美容への貢献
- 時間短縮・効率化への貢献
- コミュニティ・つながりの提供
ワーク3:非連続改善のアイデア出し
以下のフレームワークで考えてみてください:
「もし◯◯だったら」思考:
- もし予算が無制限だったら何をするか?
- もし業界の常識が存在しなかったら何をするか?
- もし全く違う業界から参入するなら何をするか?
- もしお客様の行動が180度変わったらどうするか?
非連続改善の実践事例
事例1:地方の小さな書店
延長線上思考なら:
- 品揃えを少し増やす
- 価格を少し下げる
- 営業時間を少し延ばす
実際の非連続改善:
- 「本を売る店」から「知識と体験を提供する場」に転換
- カフェ併設で滞在型空間を創造
- 地域のイベントハブとして機能
- オンライン書店との差別化を図る体験価値を重視
結果: 大型チェーン店との競争を回避し、地域に愛される独自ポジションを確立
事例2:老舗の和菓子店
延長線上思考なら:
- 伝統的な和菓子の品質向上
- 価格の見直し
- 店舗の改装
実際の非連続改善:
- 「伝統の継承」から「伝統の進化」にコンセプト変更
- SNS映えする新しい和菓子の開発
- 和菓子作り体験教室の開催
- 企業向けギフト市場への本格参入
結果: 新しい顧客層を獲得し、売上が前年比200%に向上
非連続改善を阻む「3つの壁」とその突破法
壁1:「うちの業界は特殊だから」
突破法: 他業界の成功事例を積極的に研究し、自分の業界に応用できる要素を見つける
壁2:「お客さんが求めていない」
突破法: お客さんが求めているのは「手段」ではなく「結果」。真のニーズを深掘りする
壁3:「リスクが大きすぎる」
突破法: 小さなテストから始めて、段階的にリスクを管理しながら拡大する
まとめ:勇気ある一歩が未来を変える
延長線上の改善は安全に見えますが、実は最もリスクの高い選択です。なぜなら、現状維持は緩やかな衰退を意味するからです。
市場は常に変化し、顧客のニーズも進化し続けています。延長線上の改善では、この変化の速度に追いつけません。
真の成長と成功を実現するためには、勇気を持って非連続な改善に取り組む必要があります。
最初は小さな一歩で構いません。今日から、業界の常識を1つ疑ってみてください。その疑問が、あなたの事業を次のレベルに押し上げる革命の始まりになるかもしれません。
次のステップ
非連続改善の重要性を理解したら、次は24時間という限られた時間をどう活用するかについて学びましょう。
次回の記事「24時間の使い方があなたの人生を決定する科学的根拠」では、時間の使い方が人生に与える科学的影響と、効果的な時間活用法について詳しく解説します。
今日のアクション: あなたの事業の「当たり前」を1つ選んで、「なぜこれが当たり前なのか?」を深く考えてみてください。そして、「もしこの当たり前がなかったら、どんな新しい可能性があるか?」を5分間自由に発想してみてください。この思考練習が、非連続改善への第一歩となります。
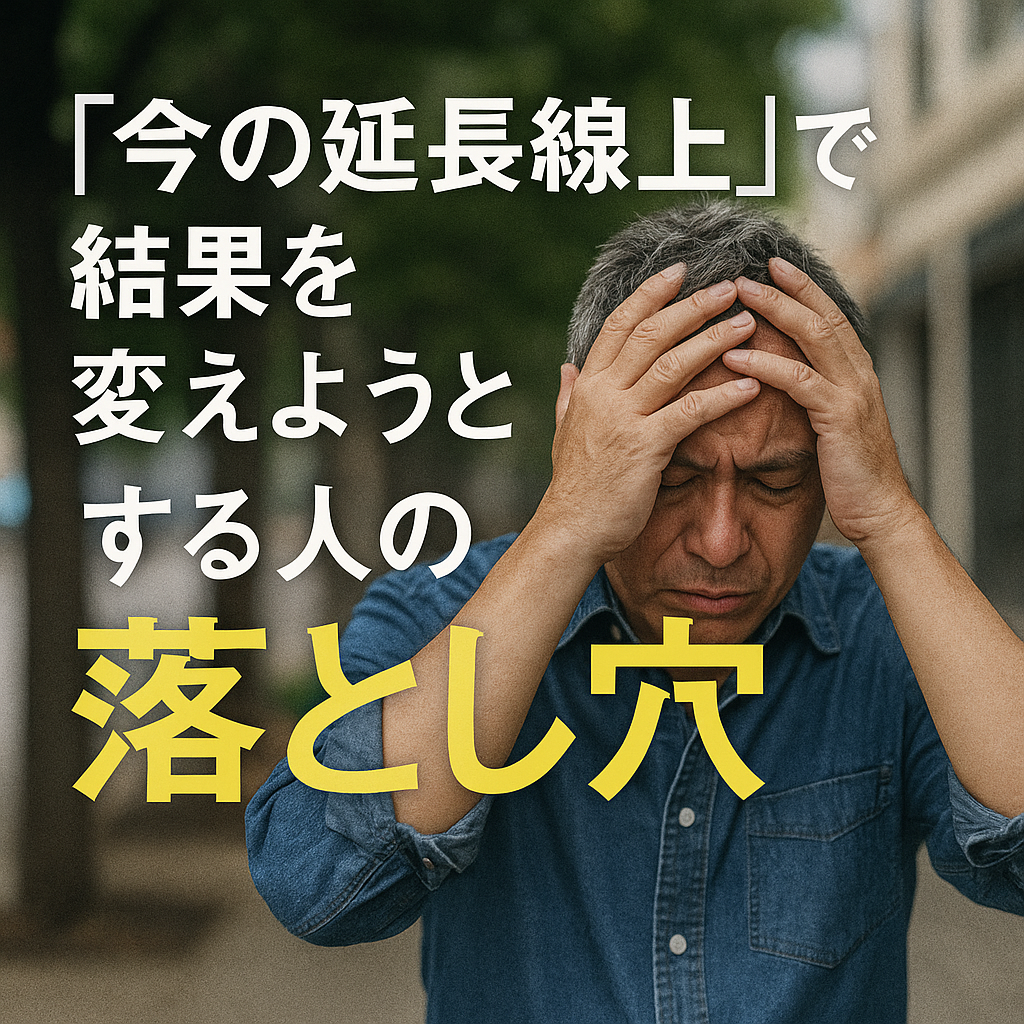


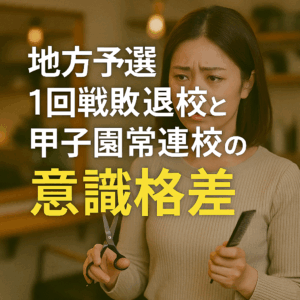
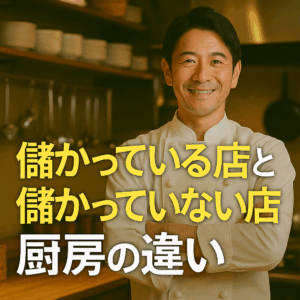
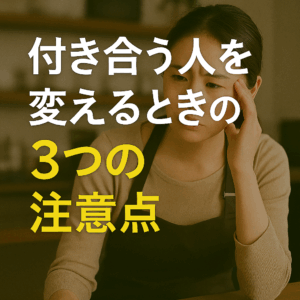


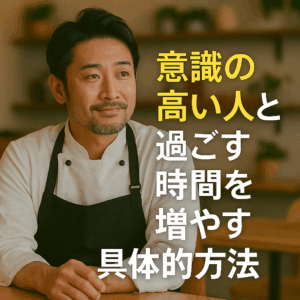
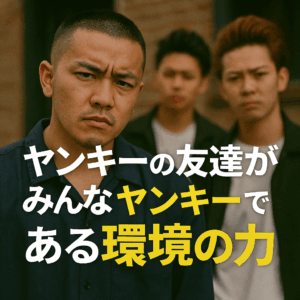
コメント